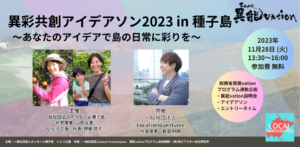こんにちは!情報発信担当のにしがきゆうこです。→自己紹介はこちら
これからLocal Innoventuresの情報発信を担当していくということで、まずは理事長の薮田明朗さんに、薮田さんのこと、地方創生のこと、そしてLocal Innoventuresのことなど、いろいろとお話をお伺いしました。
その内容を、インタビュー形式でご紹介します。
ローカルイノベンチャーズを立ち上げたきっかけ
どういう思いがあって、ローカルイノベンチャーズを始めたんですか?
もともと、こんな団体や法人を作ろうということは全く考えていなかったんですけど、学生のときからずっと、「自分は何者なんだろう」「何がしたいんだろう」ということを模索していたんです。
そのまま社会人になって、結婚して、一般的なサラリーマン生活を送る中でも、何か違うなぁというモヤモヤ感を感じながら過ごしていました。
そんなとき、東日本大震災が起こって。妻は出産後で子どもの顔を見せに、故郷の青森に帰っていたときだったんです。大きな被害があったわけではないですが、インフラが機能しない状態でしばらく過ごしていたのに、遠くにいた自分にはすぐに家族を助けるための動きができませんでした。この経験から、自分の人生をもう一度見つめ直し、もっと主体性のある人生を過ごしたいと思うようになりました。
自分の人生を改めて見つめ直す中で、「社会起業家」という役割を知り、これは自分の目指すべき方向にかなり近い活動だと感じました
震災が人生を見直すきっかけになったんですね
ただ、社会課題って多岐にわたる中で、多くの人は身近な課題だったり、何か特定の問題に絞って活動するわけですが、自分がどんな課題に対して活動するかいろいろ考えてみても、結局選べなかったんですよ。
なので、特定の課題に注力するよりも、自分以上に特定の課題に対して「自分ごと」で動いている方々を支援できる体制を作りたいと考えるようになりました。
さらに、親戚や知人が全国のあちこちにいて、どの地域の課題も気になって絞れないので、それならと風呂敷を広げてみたところ、全国どの地域にも通じるものとして「地方創生」というところに辿り着いたわけです。
各地域でそれぞれ、地域の社会課題を解決するために動く人々はいても、そこをつなぐ仕組みがなかったので、その人たちをつなぐプラットフォームづくりやその人たちの支援を行うことにしました。
地方創生と地域活性化
地方創生ってよく聞きますが、結局のところどういうことですか?
日本は今、人口が減っているんですよね。それは、国として大きな課題の一つです。そして、その次に問題になっているのは、東京一極集中。経済も人口も、ざっくり言うと半分が東京や関東圏に固まっているんです。
これらの課題を解決するために、国は地域経済の発展と持続可能な地域社会づくりを掲げていて、各地域で活性化を目指すことが「地方創生」です。簡単に言うと、人口が減り東京に集中する流れをなんとか切り替え、地域が発展することで、そこに人が住みやすくなり、東京に行かずとも、あるいは一度出ても地元に戻って生活できるようになることを目指しています。UターンやIターンなどがしやすくなるイメージです。
コロナ禍を経てテレワークなどが普及し、東京にこだわる必要性に気づく人が増えたことも、地方創生の可能性を広げた側面があるでしょう。
「地方創生」と「地域活性化」はどう違うのでしょうか
2019年から活動してきた中で、「地域活性化」や「地域おこし」という言葉を使う人たちと、「地方創生」という言葉を使う人たち、どちらもたくさん出会ってきたんですが、それぞれの人たちの考え方、価値観や属性ってちょっと違うなっていうことに気づいたんですよ。
「地域活性化」というのは、地域で動いている方たちが使う言葉です。私たち、〇〇市で地方創生やっています、とは言わないんです。プレイヤーは、地域活性化・地域おこし・町おこしといった言葉を使います。
一方で、「地方創生」という言葉を使うのは誰かと言うと、行政関係の方や、僕たちみたいに地域外から支援に入る人たち。行政関係の方のように大きい枠組みで動いてるか、または「よそ者」として地域に関わって何かを行っている方々が使う言葉という分類ができると考えています。
ローカルイノベンチャーズが「地方創生」という言葉を使っているのは、特定の地域にがっつりプレイヤーとして入るのではなく、地域外から多様な地域の方々を巻き込んで、全体的に連携して動けるようなプラットフォームを作ろうとしているからです。僕たちの本来的な活動目的は、特定の地域に限定されるようなものではなくて、様々な地域の社会課題を解決するために動く人たちが集まるコミュニティやプラットフォームを作ることなんですよ。その本質的な活動内容を分かりやすく伝えるための言葉として「地方創生」を使っています。
ローカルイノベンチャーズの活動について
他にも同じような活動をしている団体はあるんですか
そうですね、大企業がやってるものだったり、国が主体となっているものなんかもありますね。
僕らは草の根運動的に民間主導、ボトムアップ型でやっていきたいなと思っています。他にも民間でやっている団体はあるんですけど、大体の場合は特定の地域だったりこのエリアを盛り上げるために参加を呼びかけるといったように、活動範囲が限定されがちなんです。
僕たちは、地域に偏らず、全国的な規模で、異なる地域の活動をつなぎ、混ぜていこうとしています。地域が違っても共通するところがあったり、逆に違うからこその学びもあったりします。地理的な距離があるからこそつながりにくい地域同士をつなぐ、という役割は重要だと考えています。
どのような取り組みを行うかは、どうやって決めているんですか?
それは、お話が来る場合と、こちらから働きかける場合が半々です。活動を続けてきたことで、「こんなことできませんか?」とお声がけいただくこともありますし、活動を通じてできることが増えてきた中で、「こんなことができそうだな」と思いつき、関心のありそうなお相手にこちらからお話しを持ちかけることもあります。
最終的に取り組むかどうかは、僕たちの興味関心が湧くかどうか。僕たちのミーティングでは、ブレインストーミングをついついやっちゃうんですよ。あれこれアイデアを出す中で、本当にやれそうか、面白いか、ワクワクするか、そしてその活動が地域や一緒に活動する人々のサポートや助けになるかという点を考えますね。向かう方向性と明らかに違うなと感じる場合は、できるだけやれる方法がないか考えますけど、どうしてもでお断りすることもあります。
プロジェクトはどこからスタートしていくんでしょうか
多くの場合は、ご縁から始まることが多いですね。誰かとつながって、話をしている中で自然とプロジェクトが生まれていく、そんな感じです。
僕たちが地域で活動する時は、僕たちが前に出るんじゃなくて、あくまで地域のプレイヤーの方が主催とかメインになって、僕たちはゲストとかサポートっていう立場で動くようにしてるんです。これは、その地域での活動の窓口とか評価が、地域のプレイヤーの方に行くようにするためなんですよね。僕たちが地域のプレイヤーの方の活動を後押しすることで、その方が地域で動きやすくなって、活躍の場が増えて、より深い関係性が築けるって考えてるからです。
あと、総務省や内閣官房みたいな大きな看板との連携も積極的に行っています。国から来たビジネスコンテストや制度なんかの情報を、僕たちを通じて地域のプレイヤーや民間団体に共有して、「一緒に取り組みましょう!」って働きかけたりもします。僕たちが大きな看板を引き寄せることで、地域のプレイヤーの方が、周りの人たちから「あの人はそんなところともつながりがあって、そういうすごい看板も引っ張ってこられる人なんだ」と見られるようになり、結果的にそのプレイヤーの活動への注目度も高まるんじゃないかな、って考えてるんです。こんな感じで、僕たちの本体的な活動と、連携先との活動っていう形で進めています。
一番頑張ってほしいのは、地域にいる方々と地域行政なんです。彼らがしっかりつながって動けるように、僕たちはお手伝いをしたり、基盤を作ったり、あるいはきっかけ作りをしています。特に、行政とどうつながっていいか分からないっていう地域の方や、行政も地域の方とどう連携すればいいか分かっていない、そんな状況をサポートしたいなって考えています。
ローカルイノベンチャーズの今後
活動における課題は何ですか?
絶対これが一番問題っていうのがあって。ずばり、一緒に活動してくれるメンバーが足りないことです。現在、ローカルイノベンチャーズの正式なメンバーはものすごく少ない状況です。理事候補の方はいるんですが、慎重に検討している段階ですね。
メンバーを増やすにあたっては、組織への所属意識をあんまり強く求めることは避けたいなって考えてるんです。僕自身、いくつかの団体の理事を務めているように、それぞれの活動目的とか内容に応じて、色々な場所に所属しながら柔軟に活動すれば良いと思ってるんですよ。所属することによって縛りがきつくなっちゃったり、他の団体との交流を避けたりするのは望んでなくて、もっと組織同士がごちゃ混ぜになったら良いのになって感じています。
ただ、面白いことを一緒にやろうってなると、それなりに深い関わりが必要になってきますよね。なので、理事とか会員っていう形で、どれぐらいの深さで関わりたいかによって、関わり方を選べるような体制が必要なんです。深く関わって一緒に活動を進めてくれるメンバーが、圧倒的に足りていないのが現状です。
今まで自分の時間を他の人のために使いすぎちゃって、自分個人の売上が下がるなんて問題もあったので、次はしっかりと組織を大きくするために、体制をもう一度作り直して、次のフェーズへ進む必要があるって考えて整えていっています。
目指す将来像や海外展開について教えてください
ローカルイノベンチャーズの最終的な目標は、プラットフォームとして集めた情報とか事例を海外に展開していくことです。国内の地域での活動で得られた知見とか成功事例は、海外でもすごく価値を持つ可能性があるって考えてるんですよ。
海外でも、例えば中国とか韓国とかは、日本と同じように少子高齢化が進んでいたり、昔の日本の高度経済成長期みたいに開発に伴う課題を抱えている海外の地域があるんですよね。日本は「課題先進国」なんて言われますけど、僕たちが課題を解決していくことって、同じ課題を抱える他の国々の参考になるはずなんです。課題解決先進国として、日本の知見は海外で求められてるんですよ。
今、海外との交流とか、情報を発信できるような準備をちょっとずつ進めています。日本で起こっている目の前のことが、いつか世界に出ていく可能性があるって考えているんですよ。

以上、理事長・薮田さんへのインタビュー記事でした!
いろいろとお話をお伺いすることで、まだ加わったばかりのLocal Innoventuresへの理解が少し深まりました。
次は副理事長のお二人にもお話を伺っていきたいと思います。
どうぞお楽しみに!
最新記事 by にしがきゆうこ (全て見る)
- 理事長・薮田明朗さんインタビュー - 2025年6月26日
- ライター にしがきゆうこ 自己紹介 - 2025年6月23日